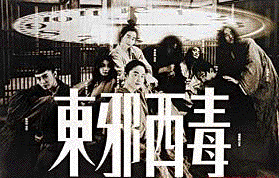楽園の瑕
(東邪西毒)
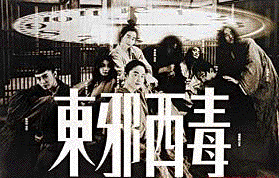
1994年製作
監督・脚本・・・王家衛(ウォン・カーウァイ)
撮影・・・・・・・クリストファー・ドイル
美術・・・・張叔平(ウィリアム・チャン)
出演
歐陽峰<西毒>・・・・張國榮(レスリー・チャン)
黄薬師<東邪>・・・・梁家輝(レオン・カーフェイ)
盲剣士・・・・・・・・・・梁朝偉(トニー・レオン)
洪七 <北夷>・・・・・張學友(ジャッキー・チョン)
燕/媛・・・・・・林青霞(ブリジッド・リン)
桃花・・・・・・・・劉嘉玲(カリーナ・ラウ)
歐陽峰の兄嫁・・・・・・・張曼玉(マギー・チャン)
村の娘・・・・・楊采[女尼](チャーリー・ヤン)
1.「楽園の瑕」が出来るまで
2.広がる続ける物語
3.歐陽峰の孤独
4.「酔生夢死」の効き目
1.「楽園の瑕」が出来るまで
映画の冒頭の言葉にあるように、これはある小説が元になっている。
というか、その武侠伝小説に登場する老人達の若い頃を想定したものということだ。例えば、原作の西毒は底意地の悪いひねた男らしいが、一体彼はどうしてそんな男になったのか、とか。
本来は東邪、西毒、北夷、南帝の4人の話であったらしい。しかしウォン・カーウァイはそんな4つの点で作られるバランスの良さを排除していった。南帝を抜き、そして当初は西毒がトニー・レオン、東邪がレスリーであったそうだ。確かに次から次へと女に関わっていくこの映画の東邪のイメージはレスリーにはまり役だったかも。
女優陣も当初はジョイ・ウォンも参加していたそうだが長引く撮影のために彼女は降板し、後にチャーリー・ヤンが参加し、そして幾度も配役の変更があったという。
また、この映画は一応正月映画として予定されていたそうだ。しかしいつもの如く撮影は延期されていき、プロデューサーだったジェフ・ラウが「楽園の瑕」のフィルムを現像している間にマッドテープとして撮影したのが「大英雄」。そしていよいよ正月映画には間に合わなくなり、「楽園の瑕」は途中で中断して、「大英雄」を僅かな日数で撮ったそうだ。
その後、冬の季節が過ぎるのを待って再び春から夏にかけて「楽園の瑕」の撮影を始めたけれど、その時に今までレスリーが東邪役で撮っていたのを西毒に変更したそうだ。更にこの2年を掛けて撮影された映画はすぐに編集されることなく、ウォン・カーウァイは「恋する惑星」を作る。その映画を経ることによって始めて「楽園の瑕」の編集に移ることが出来たということだ。(資料「ウォン・カーウァイ」ジミー・ンガイ著、「チャイニーズシネマパラダイス」ビクターエンターテイメント発行)
2.広がる続ける物語
この映画、何回見てもいいですね。
とゆーか、回を重ねるほどよくなっていくの。
まるでこの映画の衣装に使われている布の質感に似ているな。
丁寧に色を施され、よく見ると一本一本微妙な色合いを持った糸の塊が置かれている。それは毛糸玉のような完結した形ではなく、複雑に絡み合ってしかも漠然とした物だ。
しかしそこに一本の縦糸が見えてくる。それを手にとって見る。その糸の名は「黄薬師」だ。ゆっくりと引っ張りあげると、その糸には「燕/媛」と名乗る女、「盲剣士」「桃花」という糸が絡み付いているのが見えてくる。または少し離れた場所には「村の女」という糸が「盲剣士」と「洪七」をわずかにかすめるように結びつく。ところがようやくラストになって気がつくと、絡んでいた糸の塊だと思っていたものは一枚の布だった。歐陽峰のどうしようもなく切ない孤独、という名の一枚の布。
初めてこの映画を見た時、ラストで目の前にその布が表れた時、私は茫然としつつも訳も分からず涙した。そうしてこの映画も繰り返し繰り返し見ることになる。
登場人物は誰も自己主張する間を与えられていない。豪華なキャスティングだが、例えばほぼ同じキャスティングの「大英雄」の方は、俳優に対しても観客に対してもサービス心旺盛だ。「さあ、ここはあなたの見せ場だよ」というシーンがそれぞれのキャストにふんだんにあり、観客もそれを充分堪能できる。
それに比べるとこちらの「楽園の瑕」にはそういう類のサービス精神はない。登場人物は淡々と語られていき、「さあ、あなたの出番です!」的な感じがない。そしていつも、唐突に、なんの勿体もつけずに、ただ結果だけが目の前に晒される。
燕/援が二重人格者だということ、盲剣士の死、村の女とタマゴひとつで契約する洪七・・・。
「切ない」ということを胸に掻き抱きながら本来の場所でない所に一人生きていかなくてはいけないのが盲剣士とその妻、桃花だ。本当なら二人で素朴で幸せに生きていくはずだったのだ。しかし桃花がひととき黄薬師に心を移したことによって、二人はその場所には行き着けなかった。映画はそんな二人をまるで風を移しているように、そしてその中で微かに花が鳴っているように淡々と描いている。
ブリジッド・リン演じる女は幻の中を生きていた。黄薬師に愛されたという記憶も裏切られたという記憶も彼女の幻なのかもしれない。だからいいのだ。「あなたは誰を愛してるの?」という問いに代わりに歐陽峰が「君かな」と答えても。幻の黄薬師の声を聞き、そして彼を愛撫した。彼女の思いはそれで満たされたのかもしれない。彼女は確かに孤独だ。彼女の上げる雄叫びは切なく痛々しい。しかし幻の中で剣を振るい続けるだろう。もしかしたら彼女は孤独であるということに気付かないまま、凛として剣を振るっているのかもしれない。
すべての登場人物がなんともいえない深いこだまのような物を残して映画の中から消えていく。不思議なうねりを持って。そして残されたのは、孤独に気付かなかった歐陽峰だ。

3.歐陽峰の孤独
歐陽峰の仕事は殺しの仲介人だ。「殺してほしい」という人間と交渉し、それを実行してくれる殺し屋を手配する。報酬の交渉もすれば、殺し屋の生活の面倒も見る。ある意味、非常に人間臭い仕事である。
そんな歐陽峰の前にはいろんな人間が現われる。彼はその前でいつも超然としている。実際には、彼らを観察し、彼らに少しばかりの興味を抱き、時には嫉妬しようとも。それでもその姿勢は崩さない。
例えば、いつもの如く啓蟄の日にやってきた黄薬師は、次の朝にふらっと何かを思い出すようにして立ち去っていく。その馬の走り去る音を聞いて弾かれるように外へ飛び出した歐陽峰。
燕/媛の手の愛撫に目を閉じながら、愛していた兄嫁の手の触れる感触を思い出す歐陽峰。
愛している女と共に力強く砂漠の向こうへ旅立っていく洪七の姿に嫉妬する歐陽峰。
それらの姿はどうしようもなく切なげなのに、しかし、吐かれるモノローグは淡々とし、「俺はそんなものに今更揺るぎはしない」と言っているようだ。「砂漠の向こうにはまた同じ砂漠があるだけだ。そのことを俺はよく知っている」と。
そんな彼の姿が崩れるのは、兄嫁の死を知ってからだ。多分、彼は、自分を裏切った彼女の存在を心の中に意識していたからこそ、超然としていざるをえなかった。しかし、それはもう無いのだ。黄薬師が毎年自分を訪れていたのも、黄薬師もまた兄嫁を愛していて、彼女に歐陽峰の「今」を伝えるためだったと知る。黄薬師ももう来ない。それでも初めて彼を二日だけ、待ってみる。彼が来れば、歐陽峰は兄嫁の存在を感じられるからだ。まだ妄想を続けることが出来るからだ。
その時、彼は初めて砂漠を見る。「ここへ来てから砂漠を眺めるということはしたことがなかった」とモノローグが入り、私たちはここにきて初めて歐陽峰の真の孤独を知ることになる。私は幾たびこの映画を見ても、このモノローグから最後までどうしようもなく涙が溢れてしまう。彼が淡々としながら受け止める孤独の深さが胸に突き刺さってくるのだ。彼は今まで、兄嫁のことはもう過去の事だと思っていた。そして今の自分はまあまあやっていけてるな、と。ところが実際には、彼は本当に何も見てはいなかったのだ。見つめていたものはただ一つ、過去の一瞬だったのだ。
砂漠を、空を見つめながら彼は初めてそのことを自分に認めるのだ。その時きっと、彼は彼のやり方で自分自身を抱きしめたことだろう。
映画のラストで、それぞれの登場人物が、それぞれの今いる場所で剣をふるっている。黄薬師も、独狐求敗となった燕/媛も。そして洪七と闘うことになった歐陽峰の目は、ぎらぎらと輝いている。全てから距離を置いて超然とした風を装いながら生きていた男が、髪を振り乱し、生きている刹那に目を輝かせている。
4.「酔生夢死」の効き目
私はこの手のモチーフに弱い。冒頭に登場する、黄薬師が持ってきた「酔生夢死」だ。飲めば過去を忘れられる酒。
黄薬師はなんのためらいもなく飲む。彼は本当に過去を忘れてしまいたいと思っていたからだ。酩酊し、そしてひとつずつが朧になっていく。
私はこのシーンを見ながら寺山修司の映画「さらば箱舟」を思い出していた。山崎努演じる男が、時計を手に入れてからひとつまたひとつと忘れていくシーンだ。男は焦れながら身の回りにあるひとつひとつに名前を書いていく。最初は「鍋」だとか「やかん」だとか。それでも積み上げた砂山がはかなくも崩れるように、記憶はどんどんと消滅していってしまう。小川真由美演じる男の妻も、その流れに逆らうように男が名前を貼っていくのを手伝っていく。しかし、名前の書かれた紙は増え続け、それは戸口にも家にも、そして男の胸には「俺」と、女の胸には「スエ、俺の妻」と貼られていく。しかし流れ出した砂は最後の一粒に至るまで崩れてしまうのだ。「忘れてしまった男」は、自分が何かを忘れてしまったことさえ忘れてしまう。
黄薬師には「忘れてしまうことへの畏れ」は見られない。
歐陽峰には痛切にそれがある。「記憶は悩みの源だ」といいつつ、彼はそれが消えてしまえば存在している意味さえわからなくなってしまうからだ。それでも最後には彼はその酒を飲む。歐陽峰には何の効き目も無い。その筈だ。彼は「忘れたい」と思いつつも、心の中ではそれを畏れていたからだ。それでもその酒を口にせずにはいられない姿が胸に痛い。
|